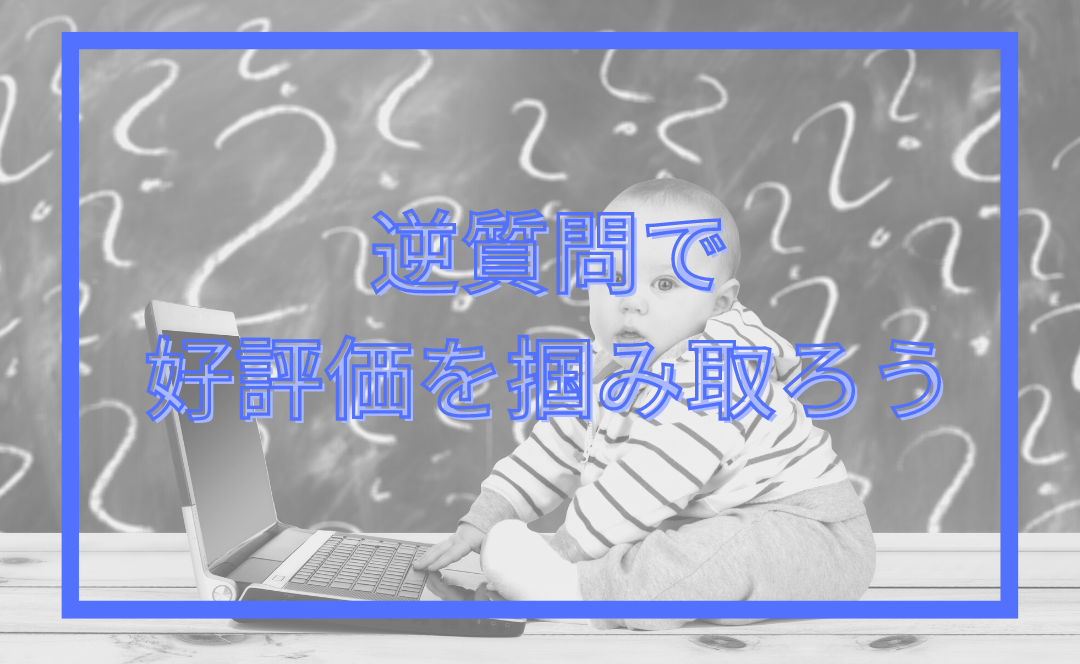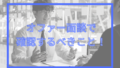転職活動の面接で必ず用意されているのが逆質問の時間。
逆質問は面接の印象を逆転するチャンスです。
ただしそれは裏を返すと、それまでの好評価も逆質問で評価が下がる可能性もあるということ。
しっかりと逆質問も対策をすることで合格へ近付くので、逆質問検討の参考にしてください。
✔️逆質問の作り方は調べたこととの差分or質問の意図がわかるように
✔️最低でも5つ程度用意しておくと安心
✔️条件面等は転職エージェントを通して質問すべし!
→おすすめエージェントは【DODA】と
逆質問をする理由
まずは面接官がなぜ逆質問の時間を設けるのかを考えましょう。
ここを理解することで、有意義な逆質問を考えることができるようになります。

まずは敵を知るところからってやつですね!
熱意が知りたい
まずはこれ。
あなたの熱意が知りたいというパターンです。
人事もあなたが1社しか受けていないとは思っていません。
だから、絶対に第1志望である必要はありません。初期の面接では特にその傾向にあります。
ですが、面接に向かってどれだけ準備をしてきたかや1つの面接に対する姿勢を通して熱意を見ています。
1つの会社と向き合う時は、そこが第1志望だという心持ちで準備しましょう。
ここがあまりにも適当だと、さすがに流れ作業すぎると見送られてしまいます。
社風との相性が見たい
逆質問は応募者の性格がかなり出ます。
ある程度メンバーに自由にさせている企業が、チームでのタスク管理がきっちりしていることを望んでいるような質問をされると「社風に合わないかな?」と思いますよね。
質問の傾向から、社風との相性は見られています。
相互理解の場(1次、2次の場合)
面接は企業があなたを判断するとともに、あなたも企業を判断する場です。
企業側からは聞きたい情報を聞き出せたため、お互いがミスマッチを起こさないように今度は企業が適切な情報を提供しますよというスタンスです。
1次面接や2次面接など、初期の面接においては逆質問も情報収集の一環と思っても良いです。
思考の傾向を見たい
逆質問を通してあなたの思考の傾向を見ていることもあります。
質問の組み立て方や内容から、どういった思考の持ち主なのかを見ています。
逆質問をする応募者のメリット
逆質問は応募者側にもメリットがあります。うまく活用しましょう。
アピールポイントにもなり得る
逆質問はアピールにもなります。
質問力が高い人は思考力に長けている印象を与えることができるんです。
それに、入念に準備をする人という点も評価ポイントになります。
ミスマッチを防げる
逆質問で情報を引き出すことで、入社後のミスマッチを防止できます。
例えばあなたはリーダーとして、チームマネジメントの経験をしたいと思っているとします。
上記のリーダー昇進までのステップを聞いた時に少なくとも10年はかかると言われたら、完全にミスマッチですよね。
このように、その会社が希望にあった職場かどうか、あなたも見定めてやるという気持ちを持っておきましょう。
逆質問で気をつけること
冒頭に書いた通り、逆質問は下手をすると評価を下げてしまうこともあり得ます。
それを防ぐためにも以下は注意しましょう。
調べたらわかることを聞かない
これは大前提です。
「ホームページにも書いてある通り〜」という話出しで返答されるともう地獄です。
質問風アピールはしない
これも辞めましょう。

え?アピールにもなるって言ってたよね?
そう疑問に感じましたか?
結果的にアピールになることと自らアピールしにいくことは全く別です。
巷のサイトでは自己アピールを含んだ質問をしましょうという情報がゴロゴロ転がっています。
「私は○○の経験がありますが、御社で活かすことはできますか?」みたいなやつです。
個人的にこれは寒すぎます。
そもそも「活かせないですね」と言われたらどうするつもりなんだろうと思ってしまいます。
逆質問は確かにアピールに繋がりますが、アピールの意味を履き違えないようにしましょうね。
面接のステップに合わせた質問を準備する
1次面接、2次面接、最終面接とステップに合わせた質問を準備するようにしましょう。
一般的なパターンとして各面接での担当者は以下のようになることが多いです。
2次面接:現場責任者
最終面接:役員や社長
それぞれの役割に合わせた質問を用意しておくことでコミュニケーション力の評価に繋がります。
最終面接でまだ業務内容の質問をしたりしていたら「業務への理解不足によるミスマッチ懸念」としてお見送りは余裕であり得ます。
質問数はある程度用意しておく
優しい企業の場合、15分以上逆質問の時間を設けてくれることがあります。
質問を1つしか用意していないとかなり時間が余って気まずいので、質問数はある程度用意しておきましょう。
最低でも5個くらいは用意しておくと困ることはないと思います。
おすすめの逆質問の作り方!
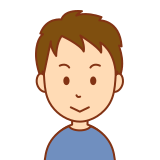
実際どんな質問をすれば良いの?
その疑問に答えるべく意識する2点をお伝えします。
両方を含んでいる必要はありません。どちらかの要素は入れておきましょうという意味です。
調べたことの差分を聞く
まずは自分で下調べをしましたよという意味も込めて、調べたけどここがわからないんですよねという質問をします。
求人情報やWantedlyなどの媒体でチームを大切にしている印象を受けました。実際に所属部署以外の方と部署の垣根を超えた業務をする機会はありますか?
こんな感じです。
恥ずかしながら、私自身が転職活動の際によくしていた質問のパターンです(笑)
求人以外の情報も見たことは面接官も悪い気はしませんし、その上での質問なので具体的なイメージを掴みたいんだなと前向きに捉えてもらえます。
この質問をすると大抵は具体例を交えて回答してもらえるので、そこからさらに深掘りみたいな感じで充実した逆質問ができます。
質問の意図がわかるようにする
質問の意図がわかることも大切です。
これはコミュニケーション力の観点です。
漠然とした質問は回答者が何を答えれば良いのか分からなくなります。
自分が知りたい情報はこれだと伝えることができるのも立派なコミュニケーション能力です。
例としては以下のような感じです。
一見似ていますが、回答者の立場になると答えやすさが全然違います。
このニュアンスの違いを理解できるようになりましょう!
×「リーダーはどうしたらなれますか?」
○「リーダー昇進までのステップはどのようになっていますか?」
逆質問で聞ききれない点は転職エージェントに質問!
上記以外でも当然聞くべきではない質問はあります。
待遇面などの話です。もちろん待遇は大切なので、入社する前に知っておくべき情報です。
給与や休日、福利厚生や労働環境など、気になる情報はたくさんありますよね。
ただ、面接の逆質問としては不適切です。

じゃあ情報はネット上と求人票しかしれない?
いいえ。そんなことはありません。
そこで活躍するのが転職エージェントです。
彼らに待遇や働く環境について質問しましょう。
求職者が直接聞けないような情報は転職エージェントが聞いてくれます。
ネガティブな情報を伝えると求職者が転職しないから隠すのでは?と不安になる方もいます。
ですが、ご安心ください。
転職者が早期離脱した場合、転職エージェントは企業へ返金対応をするような契約になっていることが多いです。
そのため、嘘の情報で転職させるのは転職エージェントにとってメリットがありません。
長く働いて活躍してくれる方が企業からの信頼も上がるので、ミスマッチを防ぐような情報提供をしてくれます。
オススメの転職エージェントを以下に記します。
DODA
言わずとしれた大手転職エージェントのDODA。
掲載求人数の多さもさることながら、その中の80%が非公開求人なので、ご自身で探すだけでは出てこない求人と出会えます。
豊富な求人の中から、あなたにぴったりの求人を紹介してくれますので、転職活動の情報収集においてはかなり有効です。
アサイン
「転職はゴールではなく、手段である」を掲げる伴走型の転職エージェントです。
求職者の希望を横流しで作業的に紹介をするのではなく、求職者のためになることを徹底しているため、価値観の深堀りから丁寧に対応してくれます。
書類の添削はもちろんのこと、面接対策もみっちりやってくれるので、最初の転職の際は登録をして損はありません。
転職エージェントについての記事はこちら
転職エージェントを掛け持ちで登録しておくべき理由やメリット、注意点は以下の記事に書いています。

ぜひ併せてご確認ください♪
逆質問も万全の準備で!
一見すると逆質問は当日のノリで行けそうと思ってしまいます。
ですが、準備をしていくことで高評価へ繋げることができることですので、万全の体勢で当日を迎えるようにしてください!